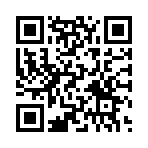2013年05月23日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-024
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-024
珊瑚礁の海岸

梅雨に入ってから雨降りの日が間断なく続いて居ります。雨の切れ間に畑の見回り。 昨日、一匹の琉球イノシシが野原を横切っていくのを見かけました。今年はサツマイモを植えておりますので、畑の垣根の柵をより強く、補強しなければなりません。ハブとイノシシの二強が揃いました。

写真は<スイジガイ>の住人の大ヤドカリ。 200mm程のスイジガイを背負って、今水槽の浄水器に組み付いているところ。 すご~いパワーです。
「壊さないでね!」


沢山あった大潮の際に採取した際の貝殻も、大分整理が付いてきました。種類別に分けてお見せしましょう。(前回とダブルところがあります)

リュウキュウヒメカタベ

結果的に「ニシキウズガイ超科カタベイ亜科」の「リュウキュウカタベ」・Angaria delphinus
となりました。少し色が褪せておりますが、生貝は綺麗なものだと思います。
↓ 45mm

下の写真は<クモガイ>の殻の裾に付着した<ヘビガイ>と <オオヘビガイ>
岩だけでなく貝殻にも付着するんですね。

次は<ガンセキボラ>です。岩礁の上やリーフの窪みに沢山居りました。大小さまざま。
水槽の中にも何匹か動いております。静かな動きですが、以外にも肉食。
死んだ<サラサバテイラ>に食い付いておりました。


下の写真は<バライロセンジュガイ>・・フィリッピン産です。 綺麗ですね。 一個だけ持ってます。

さて、次の貝殻はお馴染みの<ハナマルユキ>です。岩礁やリーフの窪みの中に潜んでおります。<ハナビラダカラ>や<キイロダカラ>と同じくらいに見られる貝でしょうか。生貝も簡単に採取できます。
30mmクラスの大きさのも結構居りますが、砂浜に落ちているものは殻が磨耗したものばかり。
ガラスのような美しい殻のものは、生で採取しなければなかなか手に入りません。
加計呂麻島ではごく一般的な貝ですね。

下の写真は現在まで蒐集したもの。細かく調べれば、珍しいタイプの<ハナマルユキ>も有りそうです。

これまた難しい貝殻が出てきました。イモガイ系統の貝は形体が非常に類似している場合が多いので、同定が可なり困難な場合があるようです。

次の例はどうでしょうか。
左の貝は生貝で採取しました。褐色の厚い皮膜を被っていましたので、漂白剤で皮膜を溶かしたのですが、なかなか完全に取れ切れません。<クロフモドキ>と同定したいのですが、図鑑によっては<アンポンクロザメ>とも見えます。左は黄色の3本の帯がハッキリと見えますので、<アンポンクロザメ>と同定できます。
保育社・「原色図鑑」では・・・アンポンクロザメガイ Lothoconus litteratus
「西表島貝殻図鑑」では・・・・クロフモドキ Lothoconus leopardus

又似たような奴が登場してきました。これも厄介ですね。<クロザメモドキ>とみるか、<ゴマフイモ>とみるか?
貝の上面の螺塔の部分が突出し、肩部には鋭い結節が並んでいるので、<ゴマフイモ>とみる。磨耗してくると同定は難しいですね。

相変わらずの<イガレイシ>ですが、右端と隣は<ムラサキイガレイシ>
左半分は「<シロイガレイシ>か、あるいは一番左は<キマダライガレイシ>の黄色の薄くなったものか??
なかなか判然としません。

本日はこの位にしておきましょう。次回も残った貝の同定をご紹介します。
姉妹ブログ
新・サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/

2013年05月16日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-023
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-023

5/14に沖縄方面が梅雨に入りました。 西南諸島・奄美大島もここ数日で入梅でしょうか?
と言ってる間に奄美も入梅・・ありゃ~!
例年は多少のずれがあるようですが、5月の月中から入梅。 梅雨明けは6月末ころ。本州とは1ヶ月のタイムラグがあるようです。 いずれにしても鬱陶しい季節になりましたと言いたいところですが、このところの乾燥した日が続いたこともあって、一安心すると言ったところが本音でしょうか。
梅雨が終わると本格的な夏が到来し、台風が訪れる季節となります。 今年は何回位ご到来でしょうか?
例年台風通過の回数が多くなるようです。 写真の右に「桟橋が見えてます。昨年の晩秋に高潮を受けて、全壊寸前になりました。運良く手早い対応ですぐに応急修理が済みましたが、今年は???
加計呂麻島の「徳浜」という珊瑚礁の中で採った、スイジガイの住人の大ヤドカリ君はその後どうなったでしょうか。

スイジガイは200mm程度ですから、中位のサイズですが、ヤドカリは結構大物でした。
殻皮に付いたコケも自然に落ちて、スイジガイ特有の地肌が見えてきました。相変わらず他の貝が数個引っ付いております。 この重い殻をいかに浮力が有ろうとはいいながら、水中を運んで行くものです。
夜中に<ゴツン、ゴツン>と殻をガラスにぶつける大きな音が、響いてきます。

少し水槽のガラスが曇っているのでハッキリしませんが、ヤドカリの触覚と脚が見えてます。水底に対して90度の角度に背負い上げています。大変なパワーです。

<ガンセキボラ>がまだ元気で水槽の底を這い回っていますね。ガンセキボラの生体は珊瑚礁の岩礁の上や小さな穴などに沢山生息しています。

<ギンタカハマ>がガラス面に張り付き、触手の先を水上に出してます。明日、水換えをしようと予定してます。水質が悪化しているからかもね。 でも、元気一杯。水槽の中を歩き?回っております。

ギンタカハマ

やっと、先日採取してきた貝殻や生貝の写真が撮れました。
二枚貝系の貝を並べてみました。<キクガイ>から始まって、<アワビ>、<トコブシ>、<カサガイ>系の貝類、<ナデシコ>、様々な二枚貝が並んでおります。
と簡単に言いますが、カサガイ系を一つ取ってもその種類は極めて多く複雑です。 外形が同じでも貝殻の表面の模様の多様さには戸惑ってしまいます。 それぞれ細かい品種が有るのか、それとも亜種やそれに類する違いが有るのでしょうか。まったく手付かずの貝群です。

この部分だけでも様々の種類がありすね。

保有しているこの手の貝はこのような有様です。下のケース、二段目のケース、そして三段目。 いったいどの位の数が入っているのでしょうか。 他人事じゃないんですが。 <ウンザリしてしまいそう>・・でもこの貝はデザインが素敵なんですね。

<オオベッコウガザ>のこの複雑な模様は、まさに現代数学のレベルですね。
一つの基本パターンの繰り返しでは有るのですが、偶然なのか、貝が意図して描いているのでしょうか。
人間の目から見ても素晴らしい芸術性が有りますね。
なかなかプロのデザイナーでも大変ですよ! この貝の仲間の貝殻の表面模様は素晴らしいものばかりです。
ですから、つい拾ってしまう。 生ガイは岩の裂け目に入り込んでいて、なかなか採取は難しい。
ナイフ持参で挑戦しても、無理な場合があります。
一回で一気に採らなければなりません。失敗したらOUTです。
絶対岩から離れようとしない。人間のほうが根負けします。

二枚貝は種の範囲が広いですね。貝の図鑑のグラビアを見るだけでもウンザリするほどのレパートリーの広さ。
見た目の鮮やかな美しいものもあれば、食用になる地味な貝もあり、殻中に棘を付けたような貝など・・・
その中で筆者が好んでいる、<ナデシコ>・イタヤガイ科の仲間達。
エビ漁の網に掛かることが多いとか。 場所は特定してはいませんが、時々、石浜や珊瑚礁の砂浜に落ちています。小さなものが多いので、注意していないとなかなか見つかりません。
上段は左が<ヤガスリヒヨク>、右が<タジマニシキ>、下段が<ナデシコ>です。

今までに採取した<ナデシコ>の中のいろいろな形や色合い

この他に<ニシキヒヨク>や<チヒロガイ>のような色鮮やかな、美しい模様の貝もあります。
下の写真は<ニシキヒヨク>・・・とても綺麗ですね。・・HPから参照

<チヒロガイ>の完品と断片・・・サイズの中位のもの。 大きくとも色合いが良いのはなかなか手に入りません。
拾えるのは偶然ですね。・・・これが貝拾いの妙味です。

貝は素晴らしい芸術家です。斉藤 宏 氏のHP「世界の貝」の公開ブログを観ておりますと、その貝の多様性と芸術性、数学的な美しさに圧倒されてしまいます。青い海の深みの中で、誰が見るわけでもないのに、こんなにも色彩豊かな色合いと形の洗練された造形を、貝たちはどのようなメカニズムを持って作り上げるのでしょうか。

タカラガイも素晴らしい殻を持っておりますが、いつもは目立たない外套膜で覆われ、水中ではなれない限りそれとは気付かないものです。・・・・・じゃ、何の為に素晴らしいガラス光沢の殻を持つのか?・・・誰に見せるために?
貝の持つ神秘のひとつ・・・この不思議さに人は・貝のコレクターは魅了され引き付けられるのでしょう。
筆者も貝に魅了されて一年余り。 もう、引き返せなくなりました。 加計呂麻島、奄美本島、周辺諸島・・・・沖縄、その周辺諸島、宮古島諸島、石垣島本島、先島諸島 etc オーストラリアの海岸やニューカレドニアは貝の宝庫とか・・・・夢は限りなく広がります。
ニューカレドニア
 ↑ ここの辺りに貝が落ちていますよ!
↑ ここの辺りに貝が落ちていますよ! 姉妹ブログ
http://akanechan.at.webry.info/
2013年05月12日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-022
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-022

ようやく長く続いた乾燥注意報も昨日で途切れました。一晩中の大雨。
これで畑の農作物も一息ついたようなところでしょうか。
貝の採集は五月初旬にかけての前半戦を終わりました。
生の貝や殻に石灰が付着した貝殻は、漂白剤の液に浸しておいてありましたが、
順次処理が終わったものもあります。今回はその中から一部ご紹介しましょう。
NHK の放送から掲載

先ず貝殻といったら、<タカラガイ>です。 NHKで放送された中で、紹介されたタカラガイ。
残念ながら<ナンヨウダカラ>しか、手元にはありません。残りの5種類は珍品な名物ばかりです。
下のケースには
<ホシキヌタ>、<ヤクシマダカラ>、<タルダカラ>、<クチムラサキ>、<ナツメモドキ>、<チャイロキヌタ>
<ウキダカラ>、<ハナビラダカラ>、<チドリダカラ>、<シラタマガイ>等が見えます。
生貝の採取でないので、余り良いものはありません。磨耗が進んでおります。

下のタカラガイは過去に手に入れたものです。右上の<タルダカラ>は拾いですが、可なり上等の部類です。
一番下の<ヒメホシダカラ>3個も同様に、砂浜で拾ったものです。偶然でしょう。海が荒れた日の採取です。このような日は磨耗の無い、生貝に近い貝も手に入ります。
中央部に<カノコダカラ>の比較的磨耗の少ない貝が見えます。横には<ナンヨウダカラ>が誇らしげに鎮座しています。
<ナンヨウダカラ>、<ハラダカラ>、<ウミウサギ>はフィリッピン産です。

次は<ホシダカラ> 95x65x60 残念ながら磨耗が進んでいます。可なり大きいですが。残念!
下段の<ホシダカラ>は、過去に採取した拾いのもの。殻の上部が若干磨耗あり。残念でした!

なかなかこれだけのものは、水中以外では採取が難しいですね。磨耗しやすい貝ですね。
下の貝は太平洋岸で漁師の兄ちゃんが、わざわざ潜って採取してくれた一品。
ガラスのように光か輝いておりました。早速、水槽に入れて・・・長く生きておりましたよ。
殻長は75mm位。 そこそこの大きさ。

先回のブログで、<ヤクシマダカラ>と<ムラサキイガレイシ>を子供にプレゼントした話をご紹介しましたが、残った貝はこの通りの磨耗が少しある<ヤクシマダカラ>でした。子供は大喜びでしたから、ま~いいか!
下の<ヤクシマダカラ>は拾いと水中採取の貝です。 綺麗でしょう。 ガラス光沢がたまりませんね。
タカラガイの魅力はここにもありますね。

今回残念なのは<ハチジョウダカラ>が一個も無かったことでした。去年から必死で生貝を探しているのですが、見つかりません。災害の赤土の海中への侵入が原因かも? 西南諸島方面は似たような現象があるようです。自然災害か人災か微妙なところです。
以前はこんな素晴らしいのが採取できました。 島の太平洋岸での採取。
このケースは<ハチジョウダカラ>オンリーです。 磨耗貝がたくさん入っております。
<ハチジョウダカラ>はどこへ行ったのでしょうか。

次は<アサガオガイ>です。
最近良く目に付くようになりました。
一番大きなので殻径27mm位・・・大きいほうかもしれません。

先回もご紹介しました<イボソデガイ>ですが、横に<スイジガイ>の幼貝が見えております。一見して同一種類の貝達であることが分ります。 ソデガイ科・Strombidae
<クモガイ>、<スイジガイ>、<サソリガイ>、<ノソデガイ>、<ゴホウラ>・・がその仲間。

 喫茶店でちょっと一服
喫茶店でちょっと一服 <<貝はどちらへ向いて進むの>>
上の写真を見てますと、貝の尖った方を手前に向けているのが多いですね。貝の頭は本当に尖った部分にあるのでしょうか。この置きかたは多分に人間的発想から来るものです。・・・どうして?・・・
下の貝の写真を良くご覧ください。<マガキガイ>の生態を写真に撮影したものです。
貝の触手が貝の殻の窄まったところ・・から見えております。 右に向かって進んでおります。
貝殻の殻頂の方が貝にとっては尻尾で、頭や足は貝殻の窄まった部分にあるのです。

学術書や参考書にはこんな基本的なことが書かれて居りません。水槽で飼ってみてやっと気が付きます。
貝殻を集めて同定し、且つ出来るだけ水槽で飼ったり、水中に潜って生態観察をすることが大事なことが分ります。そうしないと「畳の上の水練」になってしまいます。
筆者のような素人にはとても大事なことだと思っております。
それからもう一つ。
同系統の貝は外形がかなり違ったように見えても、水管(貝の窄まった部分)付近の形状は非常に似ていることが気が付きます。大雑把に貝のお尻と頭の形状で、ほぼ判別出来るのではないでしょうか。細かい種の同定は無理ですが。
今までに集めたイボソデガイ

上の写真のイボソデガイは加計呂麻島でもそうそう見つけることができません。拾われやすいのかもしれませんし、壊れやすく、磨耗しやすいのですね。 完品はなかなか手に入りません。実際に海中で捕獲するしかないのですね。
本日、最後の貝は先回に引き続いての<シイノミガイ>です。
左右の4個の貝は同じ種類の貝かどうか?
なかなか難しいのですね。 同じオカミミガイ科・クロヒラシイノミガイ正解でもあるし、そうとは言い切れないところもあるのです。


下の写真はいままで蒐集した<シイノミガイ>ですが、大方が<クロシイノミガイ>なんですが、中には<マダラヒラシイノミガイ>と<クロシイノミガイ>のハーフみたいなのも何個かあります。
この貝は絶滅種に該当するような貝なのですが、DNA上の混血があるようですね。
では何で区別するか。 沖縄のマニアの方の指摘がヒントでした。
殻の上面に付いた皺なのですね。
A- 縦縞模様の皺が無いもの・・貝の表面はクロ、茶、 マダラ模様・・・クロヒラシイノミガイ
B- 縦縞模様の皺が有るもの・・貝の表面にマダラ模様・・・・マダラヒラシイノミガイ
C- AとBのハーフ・・・・・・・ 薄くかすかに貝表面に皺があり、マダラ模様あり・・・???

鳥羽水族館のデター・ベースから拝借してきました。
確かに細かい縦筋が入っておりますね。
最近は分子生物学上の技術である、DNA判定が出来ますので確認してみたいですね。遺伝子上のほんのちょっとの違いからこのような現象が起こるのでしょうか。それにしても貝の歯はリアルですね。
加計呂麻島では特定の浜に転がっており居ります。

今回は以前にご紹介した貝を中心に展開してきました。次回はイモガイや毛色の変わった様々な貝をご紹介します。

姉妹ブログ
新・サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
2013年05月05日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-021
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-21

ゴールデン・ウイークも後半に入ってきましたが、なかなか貝の整理は思うように進捗しません。貝の整理よりも自宅の農作業の方が大事だからです。ちょうど春の野菜の植え付けのころ。安納芋というサツマイモの植え付け、ナスやキュウリ、キャベツ、アスパラ etc
ゴールデン・ウイークに3回ほど浜にはいり、貝殻採りや拾いをしました。でも、ホームランは有りませんでした。海が荒れた日がなかったことと、海中に潜らなかったことからでしょうが。
A

写真の貝は3回の貝の採取の成果の70%位・・・後は生貝は水槽の中と漂白液の中でというわけ。 種類別に分けるとそれなりにあるんですが。
B

C

D

その中で今回は珍しいものからご覧ください。大島海峡の<芝>という珊瑚砂の美しい海岸で、何の成果も無く不貞腐れていたとき拾った貝
殻表面・横から撮影

殻の裏側 殻の正面


初めは貝殻の上の方が破損したのかと思い、いったい何の貝の壊れたのかと思い拾ったのでした。まるで私の被っているシャッポと同じ形と色合い。 殻径35mm。うちへ帰って不貞寝してPM21時ころ床から起きて、PCのスイッチON。 沖縄の方のブログを検索しましたら、偶然にこの貝が掲載されておりました。 れっきとした貝でした。 珍しい貝の部類に入るとか・・・・へ~ツ (^-^)
| Cheilea cepacea (Broderip, 1834) (Broderip, 1834) | |
| 和名Japanese nameCommon name | フウリンチドリFUURIN-CHIDORI |
|---|
フウリンチドリは数種類あるのですが、その中の<チリメンフウリンチドリ>のようです。
「西表島貝殻館」参照
| チリメンフウリンチドリ |
| 縮緬風鈴千鳥 |
| スズメガイ科 |
| Cheilea hipponiciformis |
| ケイレア ヒッポニキフォルミス |

貝の裏の欠けたように見える突起がチェックポイントですね。短気を起こして捨てなくて良かったですね。
先日、徳浜というリーフで拾った、ヤドカリ入居中の<スイジガイ>。現在、水槽の中を歩いております。

例の奴ですね。 ヤドカリの足が見えてます。

続きましては珍しい貝という方ではないのですが、大島海峡側に偏って見られる感じがあります。
西表島では干潟と汽水域の貝だそうですが、加計呂麻島では砂浜で打ち上げられております。沖縄方面から流れて来るのでしょう。

右側 2個
クロヒラシイノミガイ
| |||||
| 斑平椎の実貝 | |||||
| オカミミガイ科 | |||||
| Pythia pantherina | |||||
| ピュティア パンテリナ |


下の写真は同じスイジガイを成貝・小型の成貝・幼貝(上記の貝) を並べたものです。不思議なのは右端の幼貝と隣の成貝の殻の大きさが同じというか、幼貝の方が大きいのです。このようなアンアンバランスなものが数多く見られるのです。
スイジガイの種類の相違なのか、地域差なのかは不明です。いずれも加計呂麻島周辺で採取したものです。

下の写真は同じアクッキガイ科の<クモガイ>の成貝から幼貝の例です。この例はバランスが取れていますが、かなり大きな幼貝も見られますし、また逆に小さな成貝もありますね。少し研究してみる必要ありでしょうか。

左がクモガイの幼貝、右がスイジガイの幼貝

さて、次は
下の写真の小さな穴・・・結構これが多いんですね。<ツメタガイ>という貝の仕業です。貝の中には肉食の貝が生息しております。


この他にアンボイナやタガヤサンミナシというような、人間でも殺してしまう怖い奴がおります。イモガイの仲間は大体毒があるそうで、強弱の程度でしょうか。窄まった部分は持つとき要注意ですよ!・・出てきましたね (^~^)
左・アンボイナ/90mm 右・タガヤサンミナシ/70mm

実際の海中での様子が分らないので、怖いですね。 加計呂麻島でも死亡者出ております。陸上は毒蛇・・マムシやハブ。 海中は毒貝。海蛇も相当なものらしい。
本日はこの位にしておきます。貝の処理が出来ましたら続いてご紹介しましょう。
番外編 ・・結構浜に打ち上がっております。釣り針が危ないのですがね~。

姉妹ブログ
新・サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
2013年05月01日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-020
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-020
加計呂麻島 徳浜ビーチ

連休の前半での大潮がやって来ました。
加計呂麻島の東端にある、島最大の珊瑚礁のリーフに行ってきました。
自宅から1.5時間位のところですが、何時行っても成果が余り良くありません。
崖から転落しそうになったり、岩場で腰を打って酷い目に遭いました。
今回も期待したほどの成果は有りませんでした。
生の<タカラガイ>を期待していたのですが、採り方が不味いのかさっぱり。
貝殻ばかりでした。水中眼鏡を付けてインノーの中を数m潜らなければいけないのかもしれません。
岩礁で捕獲した貝は現在水槽の中と漂白剤液の中に入れてあります。お見せするのに少々時間が必要ですので、本日はごく一部だけです。
スイジガイ・・・・加計呂麻島では火難避けとして使います

リーフの先端の岩礁の端でひっくり返っておりました。大きさは中位の200mm程度。
厚い殻皮に覆われております。いかにも生貝という感じ・・・?
よく見ますと<ヤドカリ>が入っておりました。海中をこんな重いものを担いで歩く??
水槽の中のヤドカリさん

上に方から<ギンタカハマ>がぶら下がっております。ガラス面でもどこにでも引っ付いて、水槽の中を動き回っております。海草やミドリ藻などが好きなようですので、新しい海水に混ぜて時々投入します。

<ハナビラダカラ>、<キイロダカラ>がガラス面に引っ付いております。
殻の外側を外套膜で覆っておりますので、見掛けでは慣れないと分かりません。

何種類かの生貝や殻を背負ったヤドカリがうろうろして居ります。海中から捕獲して来ておりますので、貝の磨耗がありません。
レイシガイの仲間やノシメガンセキやセンジュガイの仲間が、珊瑚礁の棚の窪みに沢山転がっておりました。 一つだけ採取して後は<もうすぐ潮が満ちてくるから、隠れろよ!>と言い聞かせながらポィ!と海中に投げ入れてやります。
辺りには集落の叔父さん叔母さんがうろうろしてますからね。
何個海に捨ててやりましたでしょうか。10個以上はありましたでしょうか。
水槽用は一個でよいのです。 食用は考えてませんのでね。
<マガキガイ>は食用にとかなり人気が有るようです。小遣い稼ぎにはなるとか。

<ムラサキイガレイシ>の生体は初めて捕獲しました。
浜から帰るとき一組の家族連れの方に同じ貝殻を見せてあげましたら、真顔で<何て綺麗!>と驚きの声を上げておりましたので、ヤクシマダカラ(貝殻)と一緒にこの貝もプレゼント。 小さな連れの子供が大喜び!・・・・こちらも嬉しいね(^-^)
このような感じのペアーでした。

ヤクシマダカラは少し惜しかった(磨耗なしの美品)。でもいいか!
子供が自然の美しさに感動することは大事なことですからね。
徳浜の右側

普通の状態はこんな感じのとても美しい浜です。
白い波が見える辺りがリーフの先端。
沖の彼方はアメリカです。
リーフの先端は急激に落ち込んでいるので、見ると怖くてブルブルします。

徳浜の左側

大きい貝は生活力も強く、狭い水槽の中でも長らく生きてくれます。
サイレント・パートナーですね。小さな貝は<ハナマルユキ>というタカラガイです。

触覚が見えますね。こんな様子は水槽で飼わないと無理ですね。
特に夜は明かりの関係でしょうか、とても美しく見えます。
海藻もさまざまな色合いがあります。
珊瑚はお花畑のような感じで見た目に綺麗なのですが、
生きているものは頑丈ですので、採ってくるのはほぼ無理。

徳浜は<ムラサキ珊瑚>が多いですね。緑色も有りますよ。

水中にはシャコガイが生息しております。左は加計呂麻近辺で見かける<ヒメシャコ>
右はモデルケース。水中で接写したらこんな感じでしょうね。


ヒメシャコは水槽でも飼えますが、水の管理が難しく金を掛けないとチョット無理かな。
水だけまめに替えてやり、光線を十分与えることが不可欠。
この電気代が馬鹿にならないとか・・・・
昨年、数個やってみましたが精々数週間位でOUTでした。
下の写真は以前古仁屋という近所の海上タクシーの待合室の水槽で飼われていたシャコガイです。光に揺らめく姿は幻想的なほど素敵ですよ!
ヒレだけでも300mm程度は有りましたでしょうか。

海の生き物は出来れば水槽で飼ってみるのが良いのですが、淡水魚と違って海水の交換が大変ですね。筆者の場合はバケツで運べば事足ります。およそ海辺から100m位の行程ですから。初めから食用にするのに生を採るのは好みません。
水槽で飼ってみて死んでからその後貝殻にすればよいのですから。
飼うことによって意外な生態が分かる場合があります。
ただ、困ることが一つ有ります。貝によっては浄水器のモーターの振動が好きらしく、給水パイプに吸い付かれて、殻とモーターのカバーが接触し、<ガーッ、ガ~>とえらい音を出してくれます。真夜中にそれで飛び起き、寝不足になりますよ。貝はマッサージ気分のでしょうか。 離れないんですね。 <マイッタ~!>(^~:)
<可愛いでしょ!>(^-^)
クマノミ

本日は貝にまつわるお話を書きました。次回は今回収穫した貝のご紹介をします。

姉妹ブログ
新・サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
 マダララシイノミガイ
マダララシイノミガイ