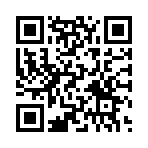2013年03月31日
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-014
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-014

月末は丁度大潮。 干潮時は0cmまで海面が下がります。
4~5月期はマイナスになりますね。
大潮の日は岩場の干上がったところは良いのですが、砂浜には何もありません。
沖のほうへ貝殻が持って行かれてしまうようです。もっぱら、石をひっくり返して貝をさがすのみ。
本日の成果・・・・やはり、良くありませんでした。めぼしい物はたったこれだけ。

<ナガニシ>、<チトセボラ>、<タルダカラ>、<ホシダカラ>
ナガニシの破損の無いものは初めて拾いました。
珊瑚の砂で殻の表面が磨耗していますが、外形は合格です。
上部ナガニシ ・下部チトセボラ 135mm

しかし、良く見てみますと、周辺の角張りが丸すぎるのに気がつきました。それで、資料を調べてみますと、イトマキボラ科には似た多様な貝が沢山有るんですね。
<イトマキボラ>、<ナガニシ>、<ポットツノマタ>、<リュウキュウツノマタ>など。
まず<イトマキボラ>
<イトマキボラ>・鳥羽水族館

外形はナガニシに似ておりますね。 角張り部分は合致します。殻の外形の模様や色は違いますが、珊瑚の砂で磨耗すると白く変化します。
次は<チトセボラ>

またまた良く似ております。しかし、螺層という横縞がハッキリ入っております。これとは違いますね。それでは、原題の<ナガニシ>は・・・
<ナガニシ>

似ておりますが、螺層が見えますし、細長く華奢ですね。ここで困りました。最後に「西表島貝類館」の助けを借りて見ました。・・有りました。そっくりな奴。
それが、下の写真。
<ボットツノマタ>・西表島貝類館

どうでしょうか?

どうもこれが正解のようです。 <ボットツノマタ>
同じ科の貝ですから、見間違いそうになるのも無理はありませんね。
加計呂麻島の西端にある「実久」で、たった一個見つけた貝です。
初めは磨耗貝と思って、欠けがないので持ち帰ったのですが、
思わぬ珍品でした。貝の名の「ボット」はミクロネシアにある環礁の名に因むのだそうです。
上記の「西表島貝類館」の資料の写真では、70mmですが、
採取したものは135mmもありました。フィリッピン辺りから流れ着いたのでしょうか。
<タルダカラ>

大分貝の同定に苦労しましたが、このような特徴のある貝で、大きなものは簡単な方で、1~2cmあるいは微小貝は素人にはお手上げの場合が多いですね。見掛けが同じでも、ちょっとした違いで、まるで違った種類のものになりますし、同じ種の貝でも地域の差から生じる、異種も有りで誠に複雑です。
さて、実久で一個拾った貝を持って、数kmの林道をUP・Downしながら、太平洋岸に行きました。阿多地、須子茂と断崖が崩れ、二車線が半車線になったような道を通って浜に辿り着きました。 <大潮の日は駄目>の通り、相変わらず・・・アカン! (^~:)

諦めて帰ろうとしてふと下を見下ろすと、白い海草の下に何か見えます。
何の気なしに拾い上げて・・・ビックリ!!・・・素晴らしいタカラガイ
数時間前に打ち上げられて、砂浜の海草に引かかった感じ。
この手の貝は太陽の光線や、雨水ですぐ貝殻の表面がくすみ、砂で磨耗されて、形が完全でもまったく価値が無いような状態になってしまいます。

写真の3個の貝の内、右の2個は以前拾った貝ですが、比較的良いほうです。今回拾った貝はまるで海中で捕獲したと同じ鮮度。 100点満点です。 偶然ですね。 初めてです。
タカラガイは海中で拾うか、生きたものを捕獲するか何れしか、良いものを手に入れることは難しいのです。
ガラスのような美しいがタカラガイの魅力なのですが、痛みやすいと言うことが難点。
例えば、下の貝は左端が、今回砂浜で拾った貝。90mmですから大物です。右2個は以前海中で捕獲した貝。85~90mm級。 光沢がまるで違うのでしょう。
生きたまま捕獲して、水槽で飼ってからその後で貝殻にしていきます。
殺しちゃ可愛そうですからね。全て太平洋岸の浜でした。
<ホシダカラ>



先程の<タルダカラ>などは、偶然の塊。良く一つだけ拾われもせず、落ちていました。
傍には小学校が有りますので、職員がマニアの場合が多く、朝早く浜に出られるとOut!
たまたま、海草が貝を覆ってくれていたので、見落としたのでしょう。
結構、こんなことが有るのです。ですから行き帰り2度同じところを通るのが鉄則。人間の眼は結構いい加減ですから、見落としは可也有るのです。
無数の石ころと貝が混同してしまうのですね。今回は個数は少なかったけれど、ラッキーでした。「諦めちゃ駄目ですね。 最後まで諦めない・・・これが鉄則!!」・・・何でもそうですがね(^-^)
次回は岩場での<ハチジョウダカラ、ヤクシマダカラ>捕獲奮戦記!
と思ったんですが、3/30の未明に、韓国と北朝鮮の雲行きが非常に悪くなってきました。グアム、サイパンへミサイルを飛ばされると、西南諸島上空を通過していきます。邀撃ミサイルが打ち落とし漏れると、精度の低い北朝鮮のミサイルは何処に落下するか分からない。
ウランは猛毒ですから、十分注意をと考えて、突如貝の採取は取り止め・・・・
仕様が無いので、自宅の裏の海岸散歩・・・何にもないさ・・・有った!
↓ アオイガイ 2cm

何故だか分からないが、この浜では<アオイガイ>が良く採れる。
よって、この浜を<へそ曲り浜>と名付けようと思います。
そのような訳で、本日は自宅待機。
「金」さん勘弁してよなあ~

姉妹ブログ
A-サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門
次回新規更改 4/06
http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/
C-茜ちゃんの生命科学入門
次回新規更改 4/06
http://blog.goo.ne.jp/amamichan/
D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>
http://blog.livedoor.jp/sawarachan/
E-茜ちゃんの<能面と能楽>
http://sawarachan.seesaa.net/
F- 日本の伝統芸術と芸能
http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/
2013年03月28日
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-013
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-013
サワラちゃん
-013
サワラちゃん

加計呂麻島西端・<芝>の珊瑚砂海岸

もう3月も終わりですね。来月は皆さんのスタートシーズンです。
上級の学校に進学する方、就職する方、転勤する方。退職して第二の人生を歩む方・・・
これからは日増しに日差しが強まり、白い珊瑚の砂浜を歩くのは、跳ね返してくる光線の強さに負けそうになります。日焼けに注意しなければ!
それでは今回は手持ちの貝の中から、似たものを同士のご紹介。
ウズラガイの仲間たち

3個とも模様や色合いが違っておりますが、<ウズラガイ>です。右端は静岡県・新井の遠州灘産。 他は加計呂麻島です。左端は<スクミウズラ>(Tonna Cepa)、隣は<ウズラガイ>(Tonnna Perdix)、右端は図鑑に掲載なし。ヤツシロガイ科(T0nnidae)に属します。
砂地の上のウズラガイ

ウズラガイの殻は軽く壊れやすいので、打ち上げ採取の完品は期待できません。皆どこか壊れております。水中で生け捕るしかありません。見かけよりも中身が多そうですね。 殻が薄いので容量が大きいのかも。完品を採取したいんですが・・・・
サツマツブリガイ(Haustellum haustellum)110mm

奄美大島近海で取れる貝ですが、紀伊半島以南からインド・西太平洋に分布します。殻は卵のように丸く水管が非常に長いのが特徴ですね。島の北端の漁師さんの家の玄関の傍の地中に刺してあるサツマツブリガイを見つけたことが有ります。この写真の倍くらい有りましたでしょうか。でも、そっと抜いてみると水管は途中で折れておりました。残念! アクキガイ科に属します。
5~50mの水深に生息するそうですが、海岸では見たことがありません。華奢な貝なので途中で破損してしまうのかもしれません。正面から見るとこんな感じです。海中で生きている姿を見てみたいですね。

同じな貝の仲間に属する貝ですが、見た目はかなり異なっておりますね。
アクキガイ

下の写真の貝はホネガイです。アクキガイと見た目には殆ど変わりないように見えます。
ホネガイ (Miurex pecten)175mm

如何でしょうか。左がアクキガイ。 右がホネガイです。棘が細かく出ているのがホネガイの特徴だとか。個別に出されると見分けは付きません。

120度おきに棘が出ております。

正面から見るとこの通り

貝の構造は幾何学的になっていることがわかります。螺旋構造、突起の出方、模様など数学を彼らはどうして知っているのかな??。 ヤドカリは磨耗した貝殻は好みません。見た目にも美しい新鮮な貝殻を好みます。どのようにして判断しているか分かりませんが。美的意識は人間並みですよ。
次回は大潮に近い日の太平洋岸の貝の採集をお送りします。

姉妹ブログ
A-サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
http://ritounikki.amamin.jp/
B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門
http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/
C-茜ちゃんの生命科学入門
http://blog.goo.ne.jp/amamichan/
D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>
http://blog.livedoor.jp/sawarachan/
E-茜ちゃんの<能面と能楽>
http://sawarachan.seesaa.net/
F- 日本の伝統芸術と芸能
http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/
2013年03月23日
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-012
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-012

今日は西南諸島は蒸し暑い感じ。昨晩も猛烈な雷雨でした。明日も雨かもね。サワラちゃんもちょっと元気がな~い。気温25℃、湿度71%・・・そうか~、これから上昇するね。
畑と貝の整理が忙しいので、貝の採取は停滞気味。3/30前後の大潮までお休み状態。

何の気なしに並べた巻貝でも、さまざまな形と殻の様子が違います。
「珊瑚礁の貝」が下に見えます。<ベニシリダカ>と<サラサバテイ>。殻径6cm程度。サラサバテイは加計呂麻島には沢山見られ15~20cm級がざらにあります。岩礁の岩の割れ目などに引っ付いて居たりします。

下の写真は5種類の巻貝です。「ニシキウズ科」に属する珊瑚礁の貝。左から<ギンタカハマ>、<ベニシリダカ>と<ニシキウズ>。
<サラサバテイラ>と<ムラサキウズ>でしょうか。

下の写真は水槽の中を移したものです。中央に<サラサバテイラ>、ガラス面に<ギンタカハマ>がくっ付いております。元気がよく水槽内を動き回っています。

さて、次はおなじみの巻貝。 さて、<クモガイ>、<スイジガイ>の何れの幼貝でしょうか?これは素人には結構難しい。

これなら幼貝でも区別は簡単。左が<クモガイ> 右が<スイジガイ>。後はこのまま巨大化して殻径25cm位になって行きます。中にはさらに大きなものも有りますが。

今整理した貝殻をケースに入れたり、ビニール袋に入れたりと様々な形で整理しております。
その1

その2

次回も整理中の貝を選んでご紹介しましょう。
姉妹ブログ
<サワラちゃんの加計呂麻日記>
http://akanechan.at.webry.info/
2013年03月18日
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-011
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記
-011

まだまだ北海道はこの通りの雪の原
寒いんですよ! でも、東京は桜が咲き始めたとか。
月末近くとなると、全国各地から桜の開花便りが届くでしょう。
<サワラちゃんの加計呂麻日記>でもお知らせしましたが、
先日、島の西端の「芝」に貝を採取に行って来ました。
芝の海岸

何時行っても、人っ子一人居ない浜。
真っ白な砂浜が広がっております。
向かい側は奄美大島です。

場所は綺麗なところでしたが、殆ど成果は上がりませんでした。
数時間も頑張って、危険な思いをしたのに、たったこれだけ。

それでも、タカラガイの割合が多かったです。
<タルダカラ>、<クチムラサキ>が有りました。
タカラガイの仲間は、珊瑚の砂で磨耗したり、日光に焼けて白化したり、
なかなか綺麗な状態の貝は拾えません。
珊瑚の砂は非常に硬いので、破損してしまいがちです。
<タルダカラ>の大きくて綺麗なものは、海中で生きている状態で捕獲しないと無理です。
ハルシャガイ(イモガイ科)

<ハルシャガイ>は珍しい貝の仲間です。これほど鮮明な色合いのものは初めて。
死後それ程の日数が経っていないのかもしれません。岩礁の潮間帯に生息します。
アオイガイ


以前にもご紹介した、貝ではなく蛸やイカの仲間で、メスのみが持つ殻です。
不思議なことに加計呂麻島の太平洋岸では見つかりません。
自宅の裏の海岸のみ。それがやっと芝でGet!
海が荒れた時、日本海側辺りから東シナ海を通って、奄美まで波に揺られて来るらしい?
ですから、海が大荒れの時のみ拾うことが出来ます。
<タコブネとアオイガイ>

<ハコダカラとクチムラサキ>・・何れも タカラガイ

<ハコダカラとクチムラサキ>・・何れも タカラガイ ・・裏

<クチムラサキ>

似たような名前の貝は多くありますが、下の貝はその一つ。
オニノツノガイは岩礁に生息し、オニノキバフデガイは砂地に生息します。
<オニノツノガイ>・・オニノツノガイ科

<オニノキバフデガイ>

オニノキバフデガイは島の東先端の徳浜の岩礁の中で採取しました。形態が類似している貝で、<チョウセンフデ>と云う貝がありますが、これも岩礁の中に見られます。
<チョウセンフデ>

貝の蒐集は博物学でもありますので、種類の正確な特定・・同定・・は結構難しいものです。蒐集は比較的簡単ですが、これらを整理して博物学的に仕分け・検証するのは大変です。でも、これが学問の楽しみでもあるのです。最近のように分子生物学が発達してきますと、精緻に検討が可能になりました。最近はDNAの鑑定までして、同定するそうです。
<サワラちゃんの加計呂麻島日記>で芝の景色が多く掲載されております。参考までに。
姉妹ブログ
<サワラちゃんの加計呂麻島日記>http://akanechan.at.webry.info/
2013年03月12日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記010
新・サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
Sawarachan
上から見下ろすと、偉くなった感じ!

先日から潮の引き方が強くなってきました。
3/14~15と月末付近は大潮です。
姉妹版の<加計呂麻日記>でもご紹介しました通り、
生間(いけんま)という、フェリーの港を通って、断崖の横の林道を巡って、
太平洋岸の加計呂麻で最大の平地がある、諸鈍の集落の海岸に向かいました。
珊瑚の白い砂が広がる、加計呂麻島の海岸

下の写真はその戦果!

中央に<クモガイ>、その下に先回ご紹介した<オニノツノガイ>がまた見えております。
今まで、大島海峡側には余りない貝と思っておりましたが、それは間違いのようです。
相変わらずクモガイの残骸が転がっておりました。
どこからか流れ着いた模様です。先回採り過ぎたので3個のみGet!
一番右端に立て一列に<ナデシコ>が見えてます。
小さな漁村の網乾し場に行くと、意外と落ちています。

いろいろな色のナデシコが有りますでしょう。
1年掛かって集めたものです。
房総半島~西太平洋に生存して、水深5m~20mの岩礁に生息場所があるそうです。
でも、なかなかお目に掛からない。右左の2枚貝なのですが、
砂浜で拾えるのは片方のみのことが多いですね。
<チサラガイ>

<ナデシコ>とは少し違ったタイプの2枚貝。こちらの貝はなかなか砂浜では手に入りません。
中には<イタヤガイ>右端下・・(帆立貝に似た貝)も見えております。
海に潜ってダイビングしながら採取するなら、もっと素晴らしいのが採れるかも。
<オニノツノガイ>、<イボソデ>、<ツノレイシガイ>、<アカイガレイシガイ>、<ガンゼキ>の仲間が見えます。

<テングニシ>、<シュマダギリ>
テングニシは殻の一部が欠けています。 シュマダギリはツメタガイに殺された模様。穴が空いてますね。
先まで尖っております。砂の磨耗もありません。・・合格!

それでも、浜辺で見つけるのは一苦労。誰かが早朝に拾っているかも・・・
近在の方はそれだけチャンスが有りますね。
でも、見落としが必ず有るのも事実。
ですから、チャンスは50%ね。

<アカイガレイシガイ>、下は<ムラサキガレイシガイ>染料の原料になるだけあって、高尚な色合い。

まだまだ、いろいろありますが、今日はこの辺で。 次回は似た名前の間違いやすい貝を。 (^-^)
姉妹ブログ
A-サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門
http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/
C-茜ちゃんの生命科学入門
http://blog.goo.ne.jp/amamichan/
D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>
http://blog.livedoor.jp/sawarachan/
E-茜ちゃんの<能面と能楽>
http://sawarachan.seesaa.net/
F- 日本の伝統芸術と芸能
http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/
2013年03月09日
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記9
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-009

-009

太平洋岸 花富

連日、晴れの日が続き、乾燥注意報が発令されていた空模様が、にわかに怪しくなってきました。
来月ともなると、いよいよ大潮の季節。
昼頃に海面がマイナスになる干潮の日は、潮干狩りのチャンスです。
近在の子供、親子がそれぞれのいでたちで、三々五々珊瑚礁のインノーと呼ばれる、
浅瀬に向かっていきます。
大型の貝・<スイジガイ>、<クモガイ>やきれいな宝貝を生きたまま捕獲出来ます。
筆者は水槽を3つ持っているので、出来るだけ生きたまま持って帰り、長く飼ってみて生態を観察します。
水槽の中には<オオベッコウガサ>、<ホシキヌタ>、<マガキガイ>、<ウズイチモンジ>などが見えてます。

貝殻は落ちている貝を無数の石や瓦礫や砂地の中から、瞬時に目の高さで好みのものを選ぶ楽しさがあります。
ほとんどの貝は欠けたり、磨耗しすぎたり、貝の表面の色模様があせてしまったりで、
なかなか選定基準に合うものは有りません。数kmも歩いて、1~2個くらいしか拾えないこともあります。
<イチモンジ>が水槽の壁面に引っ付いておりますが、このような姿は水槽ならでは・・触覚が見えてます。

海岸の岸を歩いておりますと、生魚が打ち上げられてることが有ります。
喉元を他の魚に襲われていたらしく、内蔵は有りませんでした。
生きはいいのでそのままっ持ち帰り、夕食と相成りました。
ご馳走様でした。 (^-^)

これは何だと思いますか?・・・貝が落ちているように見えますが・・
実はこれは、ヤドカリ達の集会でした。何か相談事でもあるのでしょうか。
ヤドカリは不思議な感覚を持っており、人間が見た目に美しいと感じる巻貝に、入り込む性質があります。
ですから、一時家に持ち帰り、水槽に入れて別の貝に住み替えて、空き家になった時に水槽から回収します。
磨耗が少なく、珍しい巻貝は大体そのような感じになります。
ヤドカリの世界では予想外に住宅難なのですよ。

ヤドカリの集会の際のお家の争奪戦です。結構自然界は厳しいですね。

ある日のこと、数分自宅のそばの海岸を散歩すると
何個かの貝が落ちていました。
<ヘビガイ>、5個の巻き貝、あまり落ちていない珍しい<ナデシコ>。
貝は毎朝夕の潮の道引きで一旦浜がクリアーになります。
ですから、今日は何にも落ちていなくとも、次の日はどうなるかはわかりません。
海が荒れた日の翌朝は、期待が増します。
何が落ちているかは、意外と予想出来ないのです。

<ナデシコ>はよく観察すると、<ツメタガイ>という食肉貝に襲われてしまったようです。
貝の殻の身の上の部分に、小さな穴が開けられておりました。
貝を特殊な体液で溶かしながら、穴を開け、貝の中身を溶かして食べ殺してしまうのです。

下の写真は、ずべての貝を裏返しにしたもの。 思い思いの姿で転がっています。
1~3cm内外の大きさしかありません。
目線の位置から瞬時に選分けて拾うのです。
市場で買って貝を購入する方たちには味わえない緊張感!

筆者のダイニングの中の私設・加計呂麻島研究所内はご覧のとおり。
足の踏み場もないほど貝が箱に入って、整理を待っております。
これでも種類別、科別には整理が出来ていますが、
ラベル付けはまだまだで~す。

ですから、この貝の中に新種の貝が解からないで紛れて居るかもしれません。
貝は変種や地域差が有りますので、貝図鑑に掲載されていないものも数多くあるのです。
それを、同定するのが貝の蒐集の楽しみです。
学問的に正確に分類整理するのは博物学の大変さであり、また学問をする楽しさでもあります。
鳥や蝶や魚や・・ありとあらゆる自然界の生き物、無生物を対象とする学問分野ですね。
貝は美術的、数学的な美しさを持っている蒐集対象でも有るのですね。

この中にどんな新種が有るのか・・・期待に胸膨らむ一瞬です。

貝の価値はその人その人で皆違いますが、一応市場価格はあります。
時間によっても変動します。昔は数十万(一個)、数百万円もしたものでも、
東南アジアからの流入で、大暴落したものもあります。
でも、今でも貴重なものは百万単位の金額が、オークションで付くそうですね。
もともと、「貝」は貨幣でしたから。
下手なデザインの金属貨幣なんか、及びも付かない美しいものです。
同じものがないというも、貝の性質です。
そんなに集めてどうすんの?

世界中で約10万種類、日本国内で7~8000種類、奄美海域で4000種位とされています。
絶対量は年々減少はしていますでしょうが、世代交代で新しく生まれてきますので、
皆さんで大事に保護しながら・・・・
特に死んだ貝の蒐集は自然破壊はありませんから大丈夫ですよ!
本日の一品・・<オオイトカケ>
加計呂麻島でも思わぬところに落ちていました。左側の中位の貝。
でも,拾いでは奇跡的ですね。 以後。一回もなし。
黒く見えるのは貝の蓋です。
これが有ると無いのでは貝の価格が違います。
昔はこの貝は珍品の部類でした。 大・・5.5x3.5cm 中・・3.5x2.0cm
一個数万円もしたそうです。今でも日本産は高い値段がつくそうです。


姉妹ブログ
現在、7ブログを公開しておりますが、毎週土曜日に更改をしております。
BとC 、 EとFは 隔週になることもありますのでよろしくどうぞ
!
A-サワラちゃんの加計呂麻日記
http://akanechan.at.webry.info/
B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門
http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/
C-茜ちゃんの生命科学入門
http://blog.goo.ne.jp/amamichan/
D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>
http://blog.livedoor.jp/sawarachan/
E-茜ちゃんの<能面と能楽>
http://sawarachan.seesaa.net/
F- 日本の伝統芸術と芸能
http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/
2013年03月03日
サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-008
サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記
-008

今日は久し振りの徳浜です。
白い珊瑚の砂がどこまでも続いております。
大潮の干潮の数時間前ですが、もうかなり潮は引いております。
カメラを岩礁の先に持って行きたかったのですが、もしものことを考え止め。
結果的にはそれが正解。 詳しくは<サワラちゃんの加計呂麻日記>をどうぞ!
自宅から海岸の断崖沿いに県道を1時間掛けてくる途中の、
何の変哲もない寂しい海岸の横を通りました。
海岸には岸壁の間に、小さな砂浜が申し訳程度に広がっているだけ。
そんな浜の裾に何かを感じました。 山勘!
降りて、現場に行ってみて・・一瞬・<ギョッとした>

夥しい<クモガイ>が落ちている。
欠けたもの、完品が何十個も無造作に細かいゴミと枝に混ざって転がっている。
このソファーの上だけでも42個。 完品ばかり。
破損したものはこの数倍。

特に大きなクモガイでもないですが、大きな欠けもなくまあまあの貝。

下は<ゴホウラ>という、ごろんとした貝

結構多き。 20x14x7cm 初めて拾いました。

小さい<クモガイ>は完品そのもの。中位はまあまあ。

この一種類かと思って良くゴミの間を見ていたら、<イボソデ>、<オニノキバフデガイ>がごろごろ出てきた。それも欠けもなく・・不思議なほど?
普通は数時間歩いて1個が普通。オニノキバフデの先端は必ず磨耗か欠けている。


形状も完品の10cm超。これほども数を一回なんて、普通拾いでは無理!
イボソデ=11個 オニノキバフデガイ=18個

考え込んでしまいました。その場所は漁師の民家もなく、寂しい場所。
県道の道路沿いの、何の変哲もない砂浜の岩礁の脇のゴミが寄っているところ。
どこかの場所で島人か、本土の人が海中で、貝を捕獲して身だけ取って投げ捨てたのが、
波に運ばれてこの浜に流れ着いた??
全体的にクモガイに殻皮が少なく、形状もきれいで欠けも少ない。
自然に死んだものなら、殻皮が結構付いているし、無いものは欠けが結構進んでいる。
経験的にこれは人為的な「殺貝」である。・・・明智小五郎ばりに考えた。
それにしても密漁かどうかは分からないが、初めての経験。
太平洋岸では先ずありえない。・・・・<密漁だな>・・何て(^~^)

これも磨耗も少なく、欠けもない。この貝は堅牢で簡単には壊れないが。
先にも書いたように、オニノキバフデは拾いでは、殆ど先のほうが無い。
密漁か無いか知らないが、馬鹿なことをしてくれたものだ。
筆者などは島中の人達が知り合いだから、
何も云われないが、密漁を非常に警戒している。
加計呂麻島は貝の種類は未だ豊富でしょうが、数は激減していると思う。
浜が災害で破壊され、石浜が泥浜になって居るのが多い。
これでは貝は死滅してしまう。海草も育たない。 魚も居なくなる。
昨年初めでしたら、波打ち際でレアーの魚を結構拾ったが、
最近はまったくそんなことは無くなった。
山が荒れ、自然が海山両面で破壊が進んでいると思う。
国際自然遺産に早く認定されて、修復を施さないと、
すぐに荒れた島に変わってしまう。
続きを読む